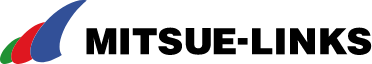ARIAを取り巻く2つの自動テスト
アクセシビリティ・エンジニア 中村(直)W3Cの年次総会に当たるTPAC 2023が9月11日から15日にかけて開催されました。アクセシビリティに関係するワーキンググループも活発にミーティングが行われましたが、ブレイクアウトセッションとして、WAI-ARIAに関係する自動テストのセッションが目を惹きました。2つのセッションについて簡単に触れたいと思います。
1つは、Cross-Browser Automated Accessibility Testing in WPT Interop 2023 and Beyondというセッションです(議事録)。
Interop 2023では、Investigation Efforts(調査の取り組み)として、Accessibility Testingが挙げられています。(Interopとは何なのかについては、フロントエンドBlogのInterop 2023がスタートをご覧ください。)
実際の議論についてはAccessibility Testing Investigation for WPT Interop 2023というGitHubレポジトリで行われており、現在WPTでARIAを含む、約600のアクセシビリティに関する自動テストが行われています(自動テストの結果)。
このセッションでは、これまでの作業の概要(該当issue)の報告や、テストの改善提案(該当issue例)の議論が行われました。
もう1つは、AT-Driver: Get Involvedというセッションです(スライド)。
AT-Driverの話に入る前に、ARIA-ATについて触れておきます。正式名称はARIA and Assistive Technology Community GroupというW3Cのコミュニティーグループです。
How Gaps in Assistive Technology Interoperability Hinder Inclusionという文書によれば、ATつまり支援技術(とくにスクリーンリーダー)は相互運用性に欠ける側面があります。
2つのスクリーンリーダー(SR1とSR2とします)を使って、あるアプリケーションを操作したときに、SR1では
Your Folders Tree View Inbox selected one of ten level one
と話される一方で、SR2では、
Your Folders Table
としか話されないとします。このように、スクリーンリーダーによって出力が異なる状況であれば、相互運用性に欠ける可能性があるということになります。
読み上げ対象箇所にARIAを用いたセマンティクスが提供されたとして、その箇所のセマンティクスがスクリーンリーダーに同じように伝わっているのか(これはSR1とSR2でまったく同じ読み上げがなされるようにするわけではないことに注意してください)について、自動テストを行うというのがARIA-ATの目標となっています。これにより、支援技術の相互運用性のギャップの解消が期待できます。
テストの結果については、ARIA-ATのTest Reportsで一覧することができます。また、ARIA Authoring Practices Guide (APG)のデザインパターンからも結果を見ることができます(例としてModal Dialog)。W3C Blogに4月に投稿されたAnswering "What ARIA can I use?"も参考になるでしょう。
前置きが長くなりましたが、この自動テストを行うにあたって利用されるAT Driverについてセッションで情報共有がされたようです。スライドによればAT-Driverは、
- プログラムによる発話の監視
- キーボード操作のシミュレーション
- 支援技術の設定の変更
といったものが行えるとあります。
このように、ARIA方面で自動テストがホットな話題になっており、標準化や互換性の向上に向けた大きな動きが見て取れ、注視していきたいと思う次第です。