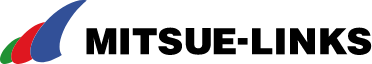生成AI全盛時代の「レディメイドとオーダーメイド」論
エグゼクティブ・フェロー木達 一仁4年前に遡りますが、私は「レディメイドとオーダーメイド」と題したコラムを書きました。十分過ぎるほどWebデザインがコモディティ化した時代においてなお、それを生業とする制作会社に生き残る術はあるのか?といった問いに対する、私なりの答えを記したコラムです。
未読でしたら、これより先を読む前に、ぜひ同コラムをお読みください。うんと端折って紹介しますと、レディメイドなWebデザインだけであらゆるニーズはカバーし得ず、差別化を可能にするオーダーメイドなWebサイトに対するニーズが存在する限り、その構築や運用を請け負う受託の制作会社に存在意義はある……といった内容です。
それから4年が経ち、さまざまな生成AIサービスが社会全体で流行している現在、Webデザインの現場においてもそれらを導入・活用する動きが盛んです。果たして「レディメイドとオーダーメイド」に記した私の主張は、生成AI全盛の今日においても、有効たり得るでしょうか?
そんな命題について考えるきっかけとなったのが、「AI Didn't Kill Web Design —Templates Did It First」という記事です。タイトルを直訳するなら「Webデザインを殺したのはAIではない、最初に殺したのはテンプレートだ」となるでしょうか。
著者のNoah Davis氏は、記事冒頭において
Let's get one thing out of the way: AI is not the villain of web design. It's just the flashy scapegoat we've all decided to blame while quietly ignoring the real killer hiding in plain sight—templates.
ひとつ、はっきりさせておきましょう。Webデザインおいて、AIは悪者ではありません。私たちは皆、テンプレートという明白な真犯人を黙って見過ごし、わかりやすい生け贄としてAIを選んだだけなのです。
と記しています。実際、多くのWebサイトで見た目が酷似しているといった指摘は、生成AIが登場するより前からあり、その背景にはコンバージョンの最大化を念頭にベストプラクティスやトレンドを織り込んだデザインテンプレートの普及がありました。
従って、ブランディング、より具体的には他のサイトと差別化したいという動機から、生成AIの隆盛とは無関係に、オーダーメイドなWebデザインへのニーズは依然として存在すると考えられます。
また、生成AIは現在進行形でWebデザインに多大な影響を及ぼしていますが、デザインした結果としてのアウトプットよりも、そのプロセスをいかに効率化できるかという切り口、側面への影響が比重を占めているように私には映ります。
そこで考えるべきは、生成AIによってオーダーメイドなWebデザインへのニーズが無くなるか?ではなく、オーダーメイドなWebサイトを将来、生成AIが構築・運用できるようになるのか?との問いでしょう。
私は敢えて「短期的には困難」と予測します。
少し話が横道に逸れますが、私の尊敬するWebデザイナーに、Jeffrey Zeldman氏がいます。かつてWeb標準が今ほど重んじられていなかった時代、彼はWeb Standards Project(WaSP)を立ち上げ、また書籍『Designing with Web Standards』を著すなどし、Web標準の普及と啓発に尽力された方です(コラム「Designing with Web Standards」参照)。
そのZeldman氏が比較的最近、SNSに投稿した内容を以下に引用します。
As vibe-coded apps and self-creating websites become the norm, luxe companies will pay large dollars for bespoke, hand-crafted HTML and CSS.
AI技術に頼ったコーディング(バイブコーディング)によるアプリやWebサイトの内製化が普及すれば、差別化を求める企業は特注の、機械に頼らず記述されたHTMLやCSSに、より多くのお金を費やすことになるでしょう。
彼が上記の投稿を行った背景や、投稿に込められた想いは、わかりません。しかし私も同感で、技術を深く理解してこそ実現できる、逆にいえば本当の意味で技術を習得していない限り実現できないレベルの差別化は、いつの時代も存在し得ると考えています。
Webデザインにおいて、生成AIが表層的な(視覚的な)レベルで差別化を実現することは、すでに現時点において可能だと思います。しかし本来、オーダーメイドなWebデザインが差別化をする対象は、見た目に限りません。
何をどう差別化すべきかは、組織と組織にとっての顧客/ユーザー双方に対する深い理解に基づくべきであって、究極それは人間そのものに対する理解度が試されることです。そのようなことが、短期間のうちに生成AIで実現可能か?と聞かれれば、どうしても私には難しく思われるのです。
そういうわけで、本コラムの結論です。「レディメイドとオーダーメイド」執筆から4年が経ってなお(また「脅威ではなく機会としての生成系AI」執筆から2年が経ってなお)私の主張に変わりはありません。ビジネスや技術、そして人間に対する興味・関心・理解を追求し続ける前提において、生成AI全盛の時代もWeb制作会社に生き残る術はある、と信じます。
Newsletter
メールニュースでは、本サイトの更新情報や業界動向などをお伝えしています。ぜひご購読ください。