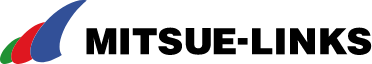ESG under fire - ESG批判の中、企業イメージを損なわずにサステナビリティを発信するには
アメリカにおいて、ESGやサステナビリティが議論の的になっているのは、誰もが認める揺るぎない事実です。
(この記事は、 Bowen Craggs社のWebサイト「Our Thinking」において2025年6月13日に公開された記事「ESG Under Fire: how to talk about sustainability without wrecking your reputation」の日本語訳です)
目まぐるしく変わる規制、偽情報の拡散、技術の進化、そして世論が二極化する今、多くの企業は批判を恐れるあまり、その場しのぎの対応を選んでしまいがちです。その結果、対応が不安定で場当たり的、一貫性がなくなってしまいます。これでは、ステークホルダーからの信頼を失い、厳しい目が向けられるでしょう。結果としてレピュテーションリスクの管理は、ますます困難になっていきます。
さらに恐ろしいのは、長い時間をかけて築き上げた透明性と信頼性のあるサステナビリティ施策が、わずか一度の報道で崩壊してしまう可能性があることです。その損失の回復には、経営者の任期や政策転換よりも長い時間が必要になるかもしれません。
Bowen CraggsのCEO、スコット氏が提唱するレピュテーションリスク管理の5つのポイントは今でも有効ですが、ESGやサステナビリティの分野では、より高度な適用が求められます。今、企業にとって重要なのは「沈黙」ではなく「戦略」です。それも企業のアイデンティティに根差し、置かれた状況に合わせて柔軟に対応でき、いかなる困難にも耐えうる戦略である必要があります。
ここでは、企業の評判や信頼性を損なうことなく、ESGとサステナビリティについて発信するための5つのポイントを紹介します。
1. 専門用語はできるだけ避ける
まずは基本知識から始めましょう
「IDKAYBIOKARTMAOEAISLEHAAOETHIOSOA」(略語の例)
(I don't know about you but I only know acronyms related to my area of expertise and it seems like everyone has an area of expertise that has its own set of acronyms.[あなたもそうかはわかりませんが、私は自分の専門分野に関連する頭字語しか知りません。また、誰もがそれぞれの専門分野に独自の頭字語のセットを持っているようです。])
サステナビリティやESGは、法務・マーケティング・現場など、社内のさまざまな部門にまたがる複雑なテーマです。だからこそ、わかりやすい言葉で説明できなければ、読み手を遠ざけ、断片的で一貫性のないメッセージを生み出すことになります。
貴社の戦略を説明するときは、6歳の子どもに話すつもりで説明してみてください。難解な言葉ではなく、だれでも理解できる表現こそが信頼される伝え方です。
2.読み手のことを理解する
「一般大衆」という人は存在しません。
たとえ専門用語を使わなくても、読み手が誰かを理解する必要があります。なぜなら、ESGに対する考え方は、人それぞれ異なるからです。ロンドンの投資家と、ワシントンの規制当局、メキシコのサプライチェーンパートナー、フィリピンのコールセンターのスタッフ、デリーの地域統括会社では、観点が全く異なります。また、アメリカ国内では、気候変動の取り組みそのものに懐疑的な人も少なくありません。
分野・業界・地域・アイデンティティ――これらは、私たちが発信するメッセージとその受け取られ方に、影響を与えます。
アメリカの名門・コーネル大学のLewis氏らが2020年に発表した研究「What Counts as an Environmental Issue?(何を環境問題とみなすのか))」によると、人種や収入水準は、何を"環境問題"と捉えるかに影響するといいます。たとえば、ある人にとっては「気候変動」が環境問題の中心でも、別の人には「食の安全」が最も切実な問題かもしれません。どちらの考えも間違いではなく、単に彼らの経験が異なるだけなのです。
Bowen Craggs社の来訪者分析のようなVisitor Researchツールを活用することで誰が貴社のWebサイトを訪れて、何を探しているのか、それが貴社への印象をどのように形成しているのかを、正確に知ることができます。また、CRMやHRISのようなシステムも、異なる視点を理解し、状況に合わせてコミュニケーションを調整するのに役立ちます。大切なのは、自分の言葉ではなく「相手の立場・関心」に合わせた言葉で発信することです。
3.組織のアイデンティティを重視する
企業のWebサイトは、どのような会社に見られるのかを心配するのではなく、本来の「自社らしさ」を反映したものであるべきです。
大事なのは、企業のミッション、ビジョン、バリューといった原点に戻ることです。これこそが、貴社らしさと、社会でどのような役割を果たしたいか、を決めるものです。新しいメッセージを発信するときも、今ある表現を見直すときも「これは自分たちらしいか?」と問いかけてみてください。
貴社を1人の人間として、その人格を捉えると、自社らしさが見えてきます。もしESGに関する発信が、批判を避けるために表面的で無難な対応にとどまっているのであれば、ステークホルダーはその姿勢を見抜くでしょう。誠実さや一貫性といった"本物らしさ"こそが、企業への信頼を築く鍵です。取り繕いはむしろ逆効果になる可能性があります。
「自社らしさ」という土台があれば、何かに振り回されることなく、自信と目的を持った行動ができるようになります。そのほうが、もっと健全なあり方ではないでしょうか。
「本当の自信」は、「リアクション(反応)」ではなく、「アクション(行動)」から生まれます。
4.マテリアリティと透明性を意識して発信する
ここで少し立ち止まって、改めて考えてみましょう。マテリアリティとは何でしょうか?それは「貴社ビジネスとステークホルダーにとって、何が重要か」に深く関連しています。それを知るために1000ページに及ぶマテリアリティ評価を委託する必要はありません。単なる情報の開示ではなく、情報を見極めることが大切です。企業にとって無関係な話題であれば、そのことを素直に伝えましょう。そして、関係する話題であれば、明確かつ丁寧に伝えましょう。そうでなければ、貴社の発信が簡単に貴社の評価を損なう原因になりかねません。実際の例を見てみましょう。
アメリカのノベルティ制作企業Sticker MuleのCEOは、2024年大統領選挙期間中に突然トランプ氏を支持するメールを顧客に送信し、ニュースになりました。アメリカのニュースサイトAxiosの報道によると、そのメールは社員1200名には相談せずに、CEOが散髪をしている際に思いつきで送ったとのことです。CEOは従業員1200人に知らせることなく、散髪中にメールを送ったそうです。新たに雇用した広報担当者は反対しましたが、彼は構わず送信しました。
Sticker Muleのミッションは「カスタムグッズを気持ちよく注文できる体験を提供すること。」従業員は17カ国に、顧客は70カ国以上に存在しています。このニュースにより、私が注文した猫のステッカーは、突然政治的な意味合いを帯びてしまいました。
それ以降、私はその企業で商品を購入することはありませんでした。
この話で伝えたいのは、「その発信が本当に自社のミッション、従業員や顧客と関係しているのか」を常に意識すべきだということです。関係のない発信をしてしまうことで、築き上げた信頼やブランド価値を一瞬で壊してしまいかねません。
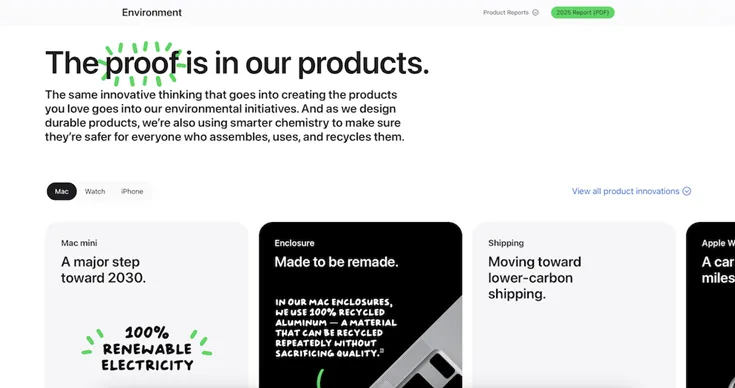
ちなみに、Appleの「環境」に関するページは、説得力のある根拠が満ちています
5.データをストーリーに紐づけて発信する
今の世の中は、誤った情報があふれていますが、本当に信頼してもらうためには根拠が必要です。ただし、事実を並べるだけでは人の心は動きません。大切なのは「ストーリーに乗せて伝えること」です。
貴社のESGデータを美術館の展示物だと考えてみてください。
- 重要な作品を厳選する
- その作品の時代背景や解説を加える
- より詳しく知りたい人のために、受付パンフレットを置く
インフォグラフィックやサイドバー、リンク、ダッシュボードなどを活用し、視覚的にも理解しやすく伝えることが重要です。生のデータをそのまま載せるだけでは、読み手の理解は期待できません。データは1つの「言語」です。誰に、何を、どう伝えるのかを意識し、相手が理解できる形に「翻訳」する必要があります。
貴社がデータを発信するときには、戦略性と創造性を持ちましょう。読む人に合わせて内容を調整し、ステークホルダーが自分の言葉で読めるようにするなど、工夫して情報ライブラリーを設計しましょう。単なる「データの羅列」ではなく、「ストーリーに乗せて」発信しましょう。
最後に、過去のデジタル資産を消さないで
リスクや不安を恐れて、自分たちの価値観を書き換えてはいけません。企業のデジタル資産には、組織の目的や信念を正しく映し出すべきです。政治的な圧力や不透明な法制度に直面すると、コンテンツを削除したり、表現を弱めたり、沈黙したりすることが安全に思えるかもしれません。しかし、ESGに関する情報を削除したり、価値観をあいまいにしたりする行為は、かえって迷いや不安を示すことになります。本当に必要なのは、後退ではなく、組織のアイデンティティと目的に根ざした一貫性のある戦略的な姿勢です。
本物の自信は「明確さ」から生まれます。自社が何を信じ、なぜそれが重要なのかを理解し、たとえ不快な状況に直面しても、一貫して発信し続けることが求められます。ESGやサステナビリティは負担ではなく、慎重かつ意図的に取り組めば、長期的な企業価値、困難を乗り越える力、リスクの管理能力を示す証拠となり得ます。
企業の評判は、プレスリリースやキャンペーン、法務部門のチェック済みの書類だけで築かれるものではありません。デジタル上のあらゆる情報に自社の価値観をどれだけ反映しているか、複雑な問題にどれだけ誠実に向き合うか、不確実な状況でもどれだけ一貫して行動するかによって、企業の評判は築かれます。